スタイルを確認するために、Material for MkDocs記法をサンプルとして記載する。
本文は、青空文庫から「芥川龍之介 - 本所両国」を借用。【青空文庫 ルビ削除ツールα版】を使わせてもらった。
Material for MkDocs記法サンプル⚓︎
Admonitions(戒め?)⚓︎
Note
「百本杭」はその名の示す通り、河岸に近い水の中に何本も立っていた乱杭である。
昔の芝居は殺し場などに多田の薬師の石切場と一しょに度々この人通りの少ない「百本杭」の河岸を使っていた。僕は夜は「百本杭」の河岸を歩いたかどうかは覚えていない。
タイトルを変える⚓︎
が朝は何度もそこに群がる
釣師の連中を眺めに行った。O君は僕のこういうのを聞き、大川でも魚のつれたことに多少の驚嘆をもらしていた。
タイトルを消す⚓︎
一度も釣竿を持ったことのない僕は「百歩杭」でつれた魚の何と何だったかを知っていない。しかし或夏の夜明けにこの河岸へ出かけて見ると、いつも多い釣師の連中は一人もそこに来ていなかった。その代りに杭の間には坊主頭の土左衛門が一人うつむけに浪にゆすられていた。……
開閉可能⚓︎
一度も釣竿を持ったことのない
一度も釣竿を持ったことのない僕は「百歩杭」でつれた魚の何と何だったかを知っていない。しかし或夏の夜明けにこの河岸へ出かけて見ると、いつも多い釣師の連中は一人もそこに来ていなかった。その代りに杭の間には坊主頭の土左衛門が一人うつむけに浪にゆすられていた。……
表現種類⚓︎
Abstract
両国橋の袂にある表忠碑も昔に変らなかった。
※他に「summary」、「tldr」。
Info
表忠碑を書いたのは日露役の陸軍総司令官大山巌公爵である。
※他に「todo」。
Tip
日露役のはじまったのは僕の中学へはいり立てだった。
※他に「hint」、「important」。
Success
明治二十五年に生れた僕は勿論日清役の事を覚えていない。
※他に「check」、「done」。
Question
しかし北清事変の時には太平という広小路(両国)の絵草紙屋へ行き、石版刷の戦争の絵を時々一枚ずつ買ったものである。
※他に「help」、「faq」。
Warning
それ等の絵には義和団の匪徒やイギリス兵などは斃れていても、日本兵は一人も、斃れていなかった。
※他に「caution」、「attention」。
Failure
僕はもうその時にも、矢張り日本兵も一人位は死んでいるのに違いないと思ったりした。
※他に「fail」、「missing」。
Danger
しかし日露役の起った時には徹頭徹尾ロシア位悪い国はないと信じていた。
※他に「error」。
Bug
僕のリアリズムは年と共に発達する訳には行かなかったのであろう。
Example
もっともそれは僕の知人なども出征していたためもあるかも知れない。
Quote
この知人は南山の戦いに鉄条網にかかって戦死してしまった。
※他に「cite」。
インラインで表示⚓︎
Info
鉄条網という言葉は今日では誰も知らない者はない。けれども日露役の起った時には全然在来の辞書にない、新しい言葉の一つだったのである。
僕は大きい表忠碑を眺め、今更のように二十年前の日本を考えずにはいられなかった。同時に又ちょっと表忠碑にも時代錯誤に近いものを感じない訳には行かなかった。
この表忠碑の後には確か両国劇場という芝居小屋の出来る筈になっていた。
現に僕は震災前にも落成しない芝居小屋の煉瓦壁を見たことを覚えている。
けれども今は薄ぎたないトタン葺きのバラックの外に何も芝居小屋らしいものは見えなかった。
もっとも僕は両国の鉄橋に愛惜を持っていないようにこの煉瓦建の芝居小屋にも格別の愛惜を持っていない。
両国橋の木造だった頃には駒止橋もこの辺に残っていた。
Info
のみならず井生村楼や二州楼という料理屋も両国橋の両側に並んでいた。
それから又すし屋の与平、うなぎ屋の須崎屋、牛肉の外にも冬になると猪や猿を食わせる豊田屋、それから回向院の表門に近い横町にあった「坊主軍鶏――」こう一々数え立てて見ると、本所でも名高い食物屋は大抵この界隈に集まっていたらしい。
富士見の渡し
僕等は両国橋の袂を左へ切れ、大川に沿って歩いて行った。「百本杭」のないことは前にも書いた通りである。しかし「伊達様」は残っているかも知れない。僕はまだ幼稚園時代からこの「伊達様」の中にある和霊神社のお神楽を見物に行ったものである。
注釈⚓︎
※有料版が必要
ボタン⚓︎
※特に使わないので省略
コードブロック⚓︎
※通常
なんでも母などの話によれば、女中の背中におぶさったまま、熱心にお神楽を見ているうちに「うんこ」をしてしまったこともあったらしい。
タイトルをつける⚓︎
トタンぶきのバラックの外に「伊達様」らしい屋敷は見えなかった。
行番号をつける⚓︎
※任意の番号から開始できる
1016 1017 1018 1019 1020 1021 | |
ハイライト⚓︎
が、渡し場らしい小屋はどこにも見えない。
僕は丁度道端に芋を洗っていた三十前後の男に渡し場の有無をたずねて見ることにした。
しかし彼は「富士見の渡し」という名前を知っていないのは勿論、渡し場のあったことさえ知らないらしかった。
「富士見の渡し」はこの河岸から「明治病院」の裏手に当る河岸へ通っていた。
その又向う河岸は掘割になり、そこに時々どこかの家の家鴨なども泳いでいたものである。
僕は中学へはいった後も或親戚を尋ねるために度々「富士見の渡し」を渡って行った。
その親戚は三遊派の「五りん」とかいうもののお上さんだった。
僕の家へ何かの拍子に円朝の息子の出入りしたりしたのもこういう親戚のあったためであろう。
タブ表記⚓︎
僕はまたその家の近所に今村次郎という標札を見付け、この名高い速記者(種々の講談の)に敬意を感じたことを覚えている。――
僕は講談というものを寄席ではほとんど聞いたことはない。 僕の知っている講釈師は先代の村井吉瓶だけである。
(もっとも典山とか伯山とか或はまた伯龍とかいう新時代の芸術家は知らない訳ではない。) 従って僕は講談を知るために大抵今村次郎の速記本によった。
しかし落語は家族達と一緒に相生町の広瀬だの米沢町(日本橋区)の立花家だのへ聞きに行ったものである。
Admonitionの中に入れる⚓︎
Error
僕はまたその家の近所に今村次郎という標札を見付け、この名高い速記者(種々の講談の)に敬意を感じたことを覚えている。――
僕は講談というものを寄席ではほとんど聞いたことはない。 僕の知っている講釈師は先代の村井吉瓶だけである。
(もっとも典山とか伯山とか或はまた伯龍とかいう新時代の芸術家は知らない訳ではない。) 従って僕は講談を知るために大抵今村次郎の速記本によった。
しかし落語は家族達と一緒に相生町の広瀬だの米沢町(日本橋区)の立花家だのへ聞きに行ったものである。
殊に度々行ったのは相生町の広瀬だった。 が、どういう落語を聞いたかは生憎はっきりと覚えていない。
ただ吉田国五郎の人形芝居を見たことだけはいまだにありありと覚えている。 しかも僕の見た人形芝居は大抵小幡小平次とか累とかいう怪談物だった。
テーブル⚓︎
| Method | Description | もう一つ |
|---|---|---|
| 僕は近頃 | 大阪へ行き、 | 久振りに文楽を見物した。 |
| けれども | 今日の文楽は | 僕の昔みた人形芝居よりも軽業じみたけれんを使っていない。 |
| 吉田国五郎の人形芝居は例えば清玄の庵室などでも、 | 血だらけな清玄の幽霊は | 太夫の見台が二つにわれると、その中から姿を現したものである。 |
ダイアグラム⚓︎
※特に使わないので省略
脚注⚓︎
※脚注はページ最下部に表示される。位置リンクが貼られる。
寄席の広瀬も焼けてしまったであろう。 今村次郎氏も「明治病院」の裏手に1ある。
そのうちに僕は震災前と――というよりむしろ二十年前と少しも変らないものを発見した2。
※脚注内で段落分けはできなさそう。
文字体裁⚓︎
取り消し⚓︎
お竹倉
僕の知人は 震災のため に、何人もこの界隈に 斃れている 。
強調⚓︎
僕の妻の親戚などは男女九人の家族中、 やっと命を全うした のは二十前後の息子だけだった。
追加⚓︎
それも 火の粉 を防ぐために戸板をかざして立っていたのを旋風のために巻き上げられ、安田家の庭の池の側へ落ちてどうかにか息を吹き返したのである。
訂正⚓︎
それから又僕は家へ 毎日のように 遊びに来た「お粂さん」という人などは命だけは助かったものの、一時は発狂したのも同様だった
ハイライト⚓︎
( 「お粂さんは」 髪の毛の薄いためにどこへも片付かずにいる人だった。
インラインコメント⚓︎
しかし髪の毛を 生やすために蝙蝠の血など を頭へ塗っていた。)
複数行ハイライト⚓︎
最後に僕の通っていた江東小学校の校長さんは両眼とも明を失った上、前年にはたった一人の息子を失い、 震災の年には御夫婦とも焼け死んでしまったとかいうことだった。 僕も本所に住んでいたとすれば、恐らくは矢張りこの界隈に火事を避けていたことであろう。 従って又僕は勿論、僕の家族もかれ等のように非業の最期を遂げていたかも知れない。 僕は高い褐色の本所会館を眺めながら、こんなことをO君と話し合ったりした。
※段落分けはできなさそう。
下線⚓︎
「しかし両国橋を渡った人は大抵助かっていたのでしょう?」
上付け、下付け⚓︎
「両国橋を渡った人はね。……それでも元町通りには高圧線の落ちたのに触れて死んだ人もあったということですよ。」
キー表記⚓︎
- Ctrl+Alt+Del
- Home+End+Tab
- Del
グリッド⚓︎
※有料版が必要
絵文字、アイコン⚓︎
※ビルトイン絵文字・アイコンの検索は公式サイト
画像⚓︎
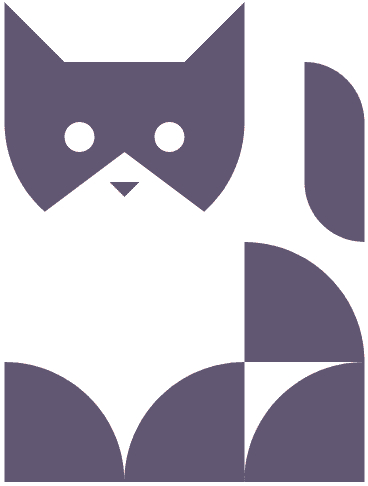
インラインで左寄せ⚓︎
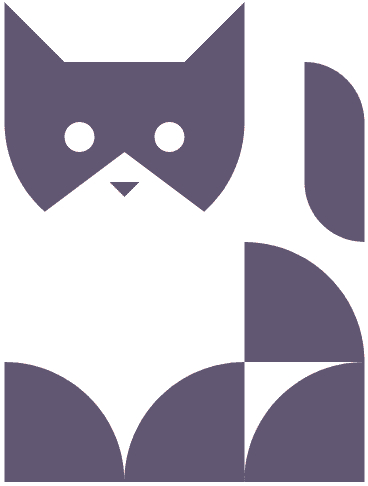
「兎に角東京中でも被服廠跡程大勢焼け死んだところはなかったのでしょう。」
こういう種々の悲劇のあったのはいずれも昔の「お竹倉」の跡である。
僕の知っていた頃の「お竹倉」は大体「御維新」前と変らなかったものの、もう総武鉄道会社の敷地の中に加えられていた。
僕はこの鉄道会社の社長の次男の友達だったから、みだりに人を入れなかった「お竹倉」の中へも遊びに行った。
そこは前にもいったように雑木林や竹やぶのある、町中には珍しい野原だったのみならず古い橋のかかった掘割さえ大川に通じていた。
僕は時々空気銃を肩にし、その竹やぶや雑木林の中に半日を暮したものである。
どぶ板の上に育った僕に自然の美しさを教えたものは何よりも先に「お竹倉」だったであろう。
インラインで右寄せ⚓︎
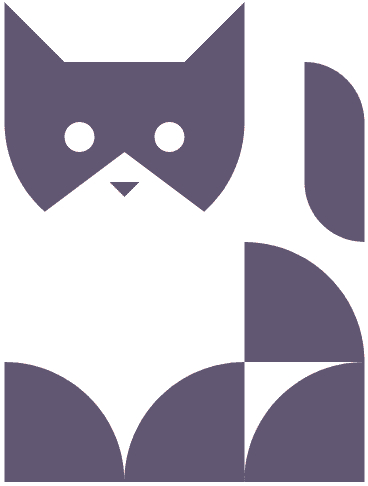
僕は中学を卒業する前に英訳の「猟人日記」を拾い読みにしながら、何度も「お竹倉」の中の景色を――「とりかぶと」の花の咲いた藪の蔭や大きい昼の月のかかった雑木林の梢を思い出したりした。
「お竹倉」は勿論その頃にはいかめしい陸軍被服廠や両国駅に変っていた。
けれども震災後の今日を思えば、――「卻って[#「卻って」は底本では「郤って」]并州を望めばこれ故郷」と支那人の歌ったものも偶然ではない。
総武鉄道の工事のはじまったのはまだ僕の小学時代だったであろう。
その以前の「お竹倉」は夜は「本所の七不思議」を思い出さずにはいられない程、もの寂しかったのに違いない。
夜は?……いや、昼間さえ僕は「お竹倉」の中を歩きながら、「おいてき堀」や「片葉の蘆」はどこかこのあたりにあるものと信じない訳には行かなかった。現に夜学に通う途中「お竹倉」の向うにばかばやしを聞き、てっきりあれは「狸ばやし」に違いないと思ったことを覚えている。
それはおそらく小学時代の僕一人の恐怖ではなかったのであろう。なんでも総武鉄道の工事中にそこへかよっていた線路工夫の一人は、宵闇の中に幽霊を見、気絶してしまったとかいうことだった。
キャプションと画像サイズ調整⚓︎
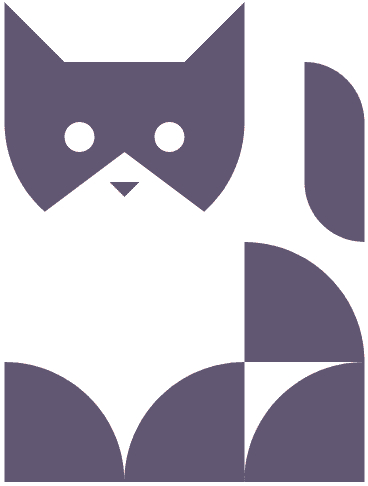
大川端
本所会館は震災前の安田家の跡に建ったのであろう。
遅延ロード⚓︎
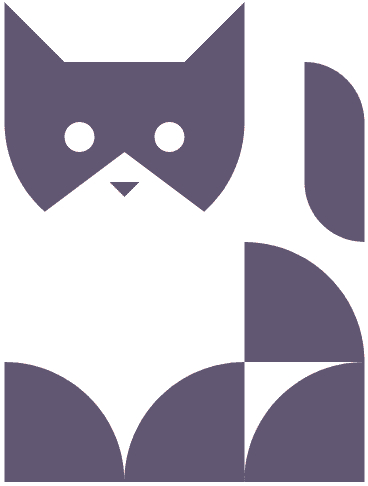
※この画像は遅延ロード設定
定義リスト⚓︎
安田家-
は確か花崗石を使ったルネサンス式の建築だった。
僕は-
椎の木などの茂った中にこの建築の立っていたのに明治時代そのものを感じている。 が、セセッション式の本所会館は「牛乳デー」とかいうもののために植込みのある玄関の前に大きいポスターを掲げたり、宣伝用の自動車を並べたりしていた。
僕の水泳を習いに行った「日本遊泳協会」は丁度、この河岸にあったものである。僕はいつか何かの本に三代将軍家光は水泳を習いに日本橋へ出かけたということを発見し、滑稽に近い今昔の感を催さない訳には行かなかった。
しかし僕等の大川へ水泳を習いに行ったということも後世には不可解に感じられるであろう。
※複数段落は無理のよう。
数式表記⚓︎
※特に使わないので省略
ツールチップ⚓︎
リンクやマウスオーバーの記載をまとめる⚓︎
アイコンに表示⚓︎
※ツールチップが設定されているかどうかわかりにくい。有料版だと改善されている?
略語⚓︎
The HTML specification is maintained by the W3C.
※日本語表記をする際には、単語両端に半角スペースを入れておく。
現に今でも O君 などは「 この川 でも泳いだりしたものですかね」と少なからず驚嘆していた。
略語定義をまとめる⚓︎
公式ページに説明あり。
pymdownx.snippets プラグインに auto_append を設定する。略語定義ファイルを指定しておけば、自動的に読み込んでツールチップ表記してくれる。
外部ファイル読み込み⚓︎
※ビルド時に完全に統合されてしまう(webアクセスごとに都度呼び出されるわけではない)ため、できあがったhtmlからはよくわからないが、外部ファイルを読み込む。
※ビルド時のカレントディレクトリからのパス指定が必要そう。うちの例だと
--8<-- "docs/others/.snippets/snippets_sample1.md"と記載する必要がある。もしくはmkdocs.ymlのオプションでbase_pathをどこかに設定するなど。
※ひとつめの読み込み
僕は又この河岸にも昔に変らないものを発見した。それは――生憎何の木かはちょっと僕には見当もつかない。
が、兎に角新芽を吹いた昔の並木の一本である。僕の覚えている柳の木は一本も今では残っていない。けれどもこの木だけは何かの拍子に火事にも焼かれずに立っているのであろう。僕は 殆どこの木の幹に手を触れてみたい 誘惑を感じた。
のみならずその木の根元には子供を連れたお婆あさんが二人曇天の大川を眺めながら、花見か何かにでも来ているように稲荷ずしを食べて話し合っていた。
※ふたつめの読み込み(コードブロックの中に読み込む)
本所会館の隣にあるのは建築中の同愛病院である。
高い鉄の櫓だの、何階建かのコンクリートの壁だの、殊に砂利を運ぶ人夫だのは確かに僕を威圧するものだった。
同時にまた工業地になった「本所の玄関」という感じを打ち込まなければ措かないものだった。
> 僕は半裸体の工夫が一人汗に身体を輝かせながら、シャベルを動かしているのを見、本所全体もこの工夫のように烈しい生活をしていることを感じた。この界隈の家々の上に五月のぼりの翻っていたのは僕の小学時代の話である。
今では――誰も五月のぼりよりは新しい日本の年中行事になったメイ・デイを思い出すのに違いない。



